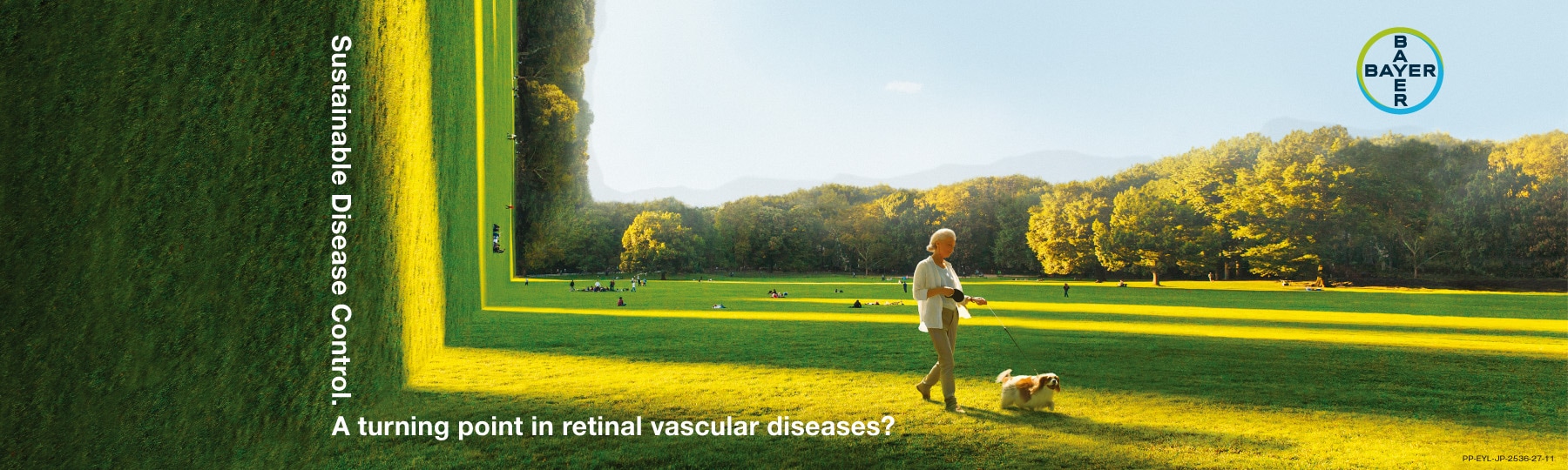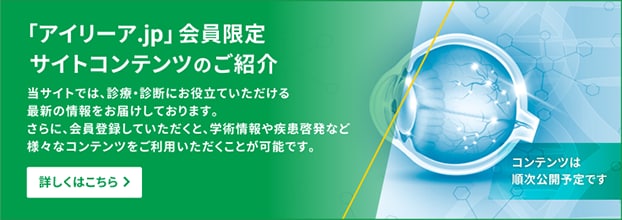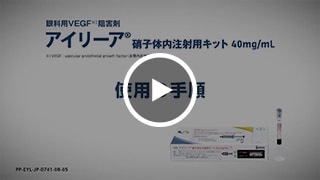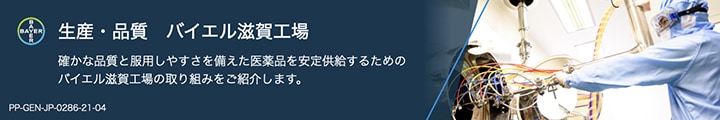このホームページで提供する情報は日本国内向けに作成されたものであり、国内での使用に限定するものです。
なお、サイト利用規約をご熟読の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。
<医療関係者の方>
このサイトは、弊社の医療用医薬品である眼科用VEGF阻害剤を正しく理解・使用していただくための情報提供サイトです。
医療関係者の皆様に適正使用の推進ならびに安全性に関する情報を提供しております。ご利用の際は、必ず注意事項をお読み下さい。
<患者さんとご家族(介護者)の方へ>
眼科用VEGF阻害剤「アイリーア®」の投与を受けられる患者さんとご家族の方のWEBページでは、「アイリーア®」による治療について正しく理解していただくために、適正使用や安全性に関する情報を提供いたします。医学的な判断やアドバイスを提供するものではないことをご理解ください。治療に関しては、必ず主治医の指示に従っていただくことが大切です。疑問を持たれたり、ご質問がある場合は、必ず医師にご相談ください。最新の正確な情報を掲載するよう努めますが、その情報の正確性、通用性、安全性について、いかなる責任を負うものでもなく、保障するものでもありません。詳しくは当社ホームページの利用規約をご確認ください。
Authentication Modal
WEBカンファレンス延長配信
(会員限定コンテンツ)

次回の開催が決まり次第、ご案内いたします。
患者さん向け眼科疾患啓発
資材お申し込みフォーム

What's New
2026/01/19
2026/01/19
2025/12/25
Copyright © Bayer Yakuhin, Ltd
- PP-EYL_8mg-JP-0761-14-01
最終更新日 2026/02/08